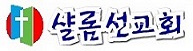▲ 일본 요코하마 해안교회는 일본 개신교회의 뿌리와 같은 곳이다.
일본 요코하마 기독교 유적지를 찾아서
뿌리 깊은 신앙 역사에서 일본선교 희망 발견
일본 기독교의 뿌리는 한국보다 깊다. 비록 역사에 비해 교세는 작지만 ‘신사의 나라’ 일본에서 기독교 신앙을 지킬 수 있었던 것은 뿌리 깊은 신앙의 역사가 있기 때문이다.
한일성결교회 공동 역사포럼에 참가한 후, 일본에 개신교가 처음 상륙한 요코하마에 있는 일본기독교 유적지를 탐방했다. 그곳에서 굴곡이 많은 일본 기독교 역사와 신앙을 만날 수 있었다.
일본 기독교의 역사
일본에 개신교가 처음 전해진 것은 1854년이다. 미국의 페리 제독이 요코하마에서 일본과 화친조약을 체결하면서 기독교 복음이 일본에 처음 상륙했다. 물론 당시에는 일본 내 개신교 선교가 불가능했고, 기독교에 대한 불신도 높았지만 미국인 영사와 의사가 일본인들에게 영어를 가르치면서 사실상 선교의 문을 열었다.
이후 1859년 일본 내 미국인들을 위해 미국 북장로교 의료선교사 헵번(Dr.J C Hepburn), 미국 성공회 윌리엄스(C Williams), 미국 개혁교회 브라운(S Brown) 선교사 등이 차례로 입국하면서 본격적인 선교활동이 시작되었다. 일본의 작은 어촌마을 요코하마는 이렇게 일본 기독교의 출발지가 되었으며, 오늘날 일본 제2의 도시로 발전하게 되었다.
일본의 첫 교회, 해안교회
일본 요코하마에서 가장 유서 깊은 기독교 유적지는 일본 최초의 교회인 해안교회(가이칸교회)이다. 해안교회는 일본 기독교의 뿌리와도 같은 곳이다. 1867년 요코하마를 방문한 한 선원이 이곳에서 기도하면서 외국인들의 예배 장소가 되었다고 한다. 이런 신앙의 뿌리가 내린지 5년 후 1872년 2월에 이곳에 정식 교회당이 세워졌다. 매년 신년이면 이곳에서 외국인들의 기도회가 열렸는데, 선교사들에게 영어를 배우던 학생들이 이 광경을 보고 기독교로 개종세례를 받으면서 일본인 성도가 생겨났다. 이후 1875년에는 예배당이 좁아 교회당을 신축했을 정도로 부흥이 됐다.
요코하마 해안교회는 아직도 처음 그 자리를 굳건히 지키고 있다. 요코하마 개항 광장 옆에 자리 잡고 있는 해안교회는 1923년 관동대지진 때 당시 교회당은 완전히 무너져 내렸지만 초기 역사와 신앙을 고스란히 간직하고 있었다. 예배 실 입구에 있는 옛 간판이 137년의 긴 역사를 보여주고 있었으며, 80년 된 교회 종도 여전히 복음의 메아리를 울리고 있었다.
특히 해안교회의 종소리는 척박한 일본 땅을 사랑한 한 선교사의 애틋한 사연이 녹아 있어 더욱 심금을 울리는 듯 했다. 초기 일본에서 선교 활동했던 한 여성 선교사가 미국으로 귀향한 후 일본 복음화를 염원하면서 1932년 종을 만들어 해안교회로 보냈다는 것. 태평양 전쟁 때 일본 군대에 의해 철거될 위기도 있었지만 한 선교사의 못 다 이룬 일본 선교의 꿈을 위해 여전히 복음의 종소리를 멈추지 않고 있다.
선교열정이 잠든 ‘외국인 묘지’
흔히 일본은 선교사의 무덤이라고 불린다. 그만큼 선교가 힘들기 때문이다. 전 세계 90여개국에서 3000여명의 선교사들이 파송돼 복음을 전하고 있지만 고전을 면치 못하고 있다. 선교 148년이 지나도록 복음화 율은 1%도 넘지 못하는 것도 이 때문이다.
그러나 처음 일본선교의 문을 여는 데는 지금보다 더 큰 어려움이 있었다. 도쿠가와 이에야스의 에도시대(1612∼1868년)에 강력한 쇄국정책으로 일본 땅에서 ‘선교’는 불가능했다. 300년 동안 잠자는 일본을 깨운 사람들은 바로 이름 없는 외국인들과 선교사들이었다.
척박한 일본 선교를 개척한 초기 기독교인들은 요코하마 외국인묘지에 잠들어 있다. 요코하마 시내와 항구가 내려다보이는 언덕에 자리 잡은 외국인묘지에는 4200여개의 십자가 무덤이 있다. 1854년 개항 이후 40개국에서 온 주재원과 선교사 등은 비록 이곳에 묻혀 있지만 그들의 일본을 향한 열정은 멀리 바라다보이는 바다만큼이나 푸르고 넓어 보였다.
신앙 선진들의 고귀한 신앙흔적을 간직하고 있는 요코하마의 기독교 유적지를 통해 일본 선교의 희망을 찾을 수 있었다.
■横浜海岸教会の歴史
西暦1859年、まだキリシタン禁教の時代に日本にキリストの福音を伝えようと、海外から非常な危険を冒して多くの宣教師等が日本に上陸して来ました。その年、神奈川に渡来したのは米国長老派教会の、J.C.へボン、米国改革派教会の、S.R.ブラウンなどでした。1861年には、米国改革派教会のJ.H.バラ夫妻が神奈川に渡来しました。
彼等はまず横浜で英語私塾を開き、同時にキリスト教の開拓的伝道のための準備を始め、1868年5月には現在の横浜海岸教会が所在する場所に、石造りの小会堂が建設されました。
1872年の初週祈祷会では連日熱心な祈りがささげられ、同年3月10日J.H.バラ(写真右下)によって篠崎桂之助(しのざきけいのすけ)以下9名の受洗が行なわれました。同日、既に他所で受洗していた2名を加え、11名で日本基督公会を設立し、バラが仮牧師となり、小川義綏(おがわよしやす)が長老、仁村守三(にむらもりぞう)が執事に就任しました。この日が横浜海岸教会の創立記念日となっています。
3年後の1875年に教会堂が建設されて、横浜海岸教会と改称されましたが、1923年の関東大震災で教会堂は壊滅し、現教会堂は1933年に再建されたものです。
毎週の主日礼拝は、第二次大戦中のキリスト教弾圧の時代にあっても-回も欠かすことなく守られてまいりました。受洗者総数は関東大震災によって記録消失のため詳細不明ですが、累計すれば約6,000名を下らないものと推計されます。
歴代牧師は以下のとおりです。
・J.H.バラ(仮牧師在任7年)
・稲垣 信(いながきあきら・前後通算22年)
・細川 瀏(ほそかわきよし・2年)
・笹倉 弥吉(ささくらやきち・35年)
・渡辺 連平(わたなべれんぺい・34年)
・井上 平三郎(いのうえへいざぶろう・11年)
・林嗣 夫(はやしつぎお・4年)
・岡田 貴美子(おかだきみこ・2年)
・久保 義宣(くぼよしのぶ・15年)
・上山 修平(うえやましゅうへい)
教会設立出発点となった1872年の初週祈祷会の折に、J.H.バラから篠崎桂之助らに与えられた聖句は旧約聖書イザヤ書第32章15節でありました。
ついに我々の上に
霊が高い天から注がれる。
荒れ野は園となり、
園は森と見なされる。
教会堂塔上から礼拝の開始を知らせるチャーチベル(写真右)は、1875年に教会堂を建設した際メアリー・プラインから寄贈されたものです。
また、庭にはその当時の記念礎石が飾られています。礼拝堂入口左側にある「日本基督横浜海岸教会」の銘板も当時のものです。
出処:
http://homepage3.nifty.com/yokohamakaiganchurch/history.html